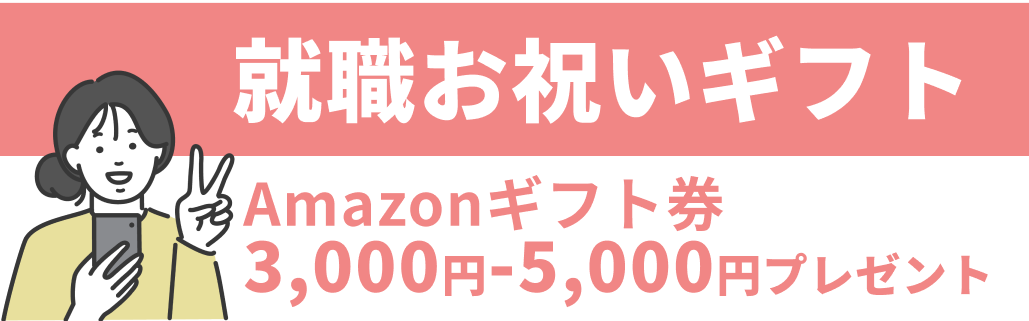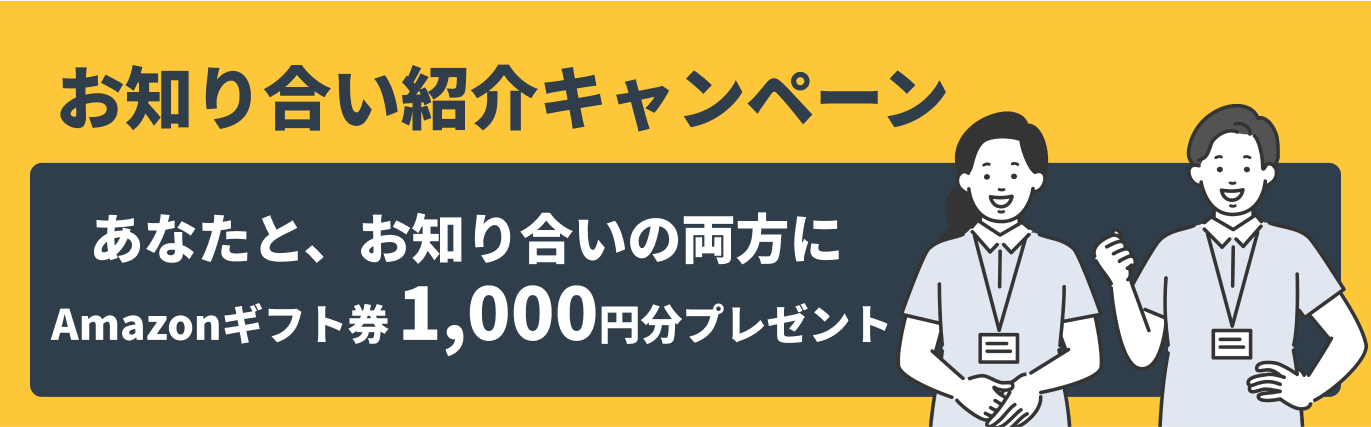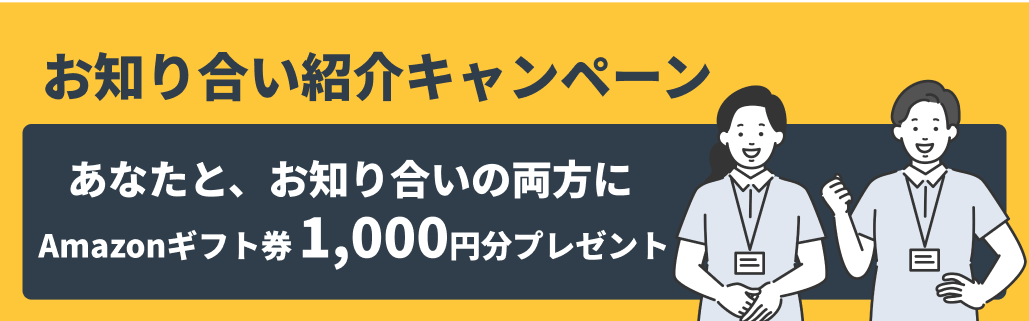職種から求人を探す
高齢福祉系
医療系
とじる
都道府県から求人を探す
とじる
こだわり条件から探す
賞与あり(6790)
年間休日110日以上(4676)
その他休暇制度あり(8959)
土日休み(571)
日勤のみ可(6755)
シフト相談可能(4858)
残業なし/残業少なめ(4061)
未経験歓迎(6475)
送迎なし可(486)
ブランクOK(4936)
中高齢者歓迎(1928)
定年65歳以上/定年なし(1619)
資格取得支援(5466)
研修制度あり(8841)
車通勤可能(4744)
駅チカ(4818)
産休・育休取得実績あり(7894)
社宅/寮/住宅手当あり(1766)
保育園/託児所あり(1256)
オープニング(1年以内)(335)
扶養内勤務可能(1244)
ダブルワーク可能(1126)
オンライン面接可能(200)
施設見学可能(429)
ふくみっとインタビューあり(218)
ちょいムビあり(ショートムービーのこと)(41)
とじる
サービス種別から求人を探す
■ 高齢福祉系
通所介護・デイサービス(1410)
訪問介護(730)
グループホーム(724)
サービス付き高齢者向け住宅(560)
訪問入浴(69)
通所リハ・デイケア(166)
特別養護老人ホーム(696)
介護老人保健施設(514)
ケアハウス(軽費老人ホーム)(27)
定期巡回・随時対応サービス(22)
介護付き有料老人ホーム(2825)
住宅型有料老人ホーム(539)
小規模多機能型居宅介護(243)
看護小規模多機能型居宅介護(77)
ショートステイ(80)
ケアプランセンター(356)
地域包括支援センター(50)
養護老人ホーム(3)
介護医療院(7)
■ 障害支援系
居宅/重度訪問介護(82)
同行/行動援護(10)
ショートステイ(14)
療養介護(0)
生活介護(117)
グループホーム(141)
自立訓練(2)
就労支援(A,B,移行)(119)
地域生活支援事業(1)
相談支援事業(12)
放課後等デイサービス(466)
施設入所支援(71)
児童発達支援(12)
■ 医療系
■ 保育系
■ その他
雇用形態から求人を探す
こだわり条件から求人を探す
賞与あり(6790)
年間休日110日以上(4676)
その他休暇制度あり(8959)
土日休み(571)
日勤のみ可(6755)
シフト相談可能(4858)
残業なし/残業少なめ(4061)
未経験歓迎(6475)
送迎なし可(486)
ブランクOK(4936)
中高齢者歓迎(1928)
定年65歳以上/定年なし(1619)
資格取得支援(5466)
研修制度あり(8841)
車通勤可能(4744)
駅チカ(4818)
産休・育休取得実績あり(7894)
社宅/寮/住宅手当あり(1766)
保育園/託児所あり(1256)
オープニング(1年以内)(335)
扶養内勤務可能(1244)
ダブルワーク可能(1126)
オンライン面接可能(200)
施設見学可能(429)
ふくみっとインタビューあり(218)
ちょいムビあり(ショートムービーのこと)(41)
資格から求人を探す
■ 高齢福祉系
介護福祉士(5890)
実務者研修(ヘルパー1級)(5284)
初任者研修(ヘルパー2級)(5103)
介護支援専門員(926)
主任介護支援専門員(145)
社会福祉士(708)
社会福祉主事任用(305)
精神保健福祉士(298)
鍼灸師(75)
あん摩マッサージ指圧師(162)
柔道整復師(303)
福祉用具専門相談員(7)
■ 医療系
正看護師(1690)
助産師(7)
保健師(23)
理学療法士(484)
作業療法士(436)
言語聴覚士(263)
視能訓練士(10)
臨床工学技士(10)
診療放射線技師(23)
臨床検査技師(30)
薬剤師(81)
歯科衛生士(7)
公認心理士(49)
臨床心理士(42)
医師(13)
准看護師(882)
■ 障害支援系
■ 保育系
■ その他
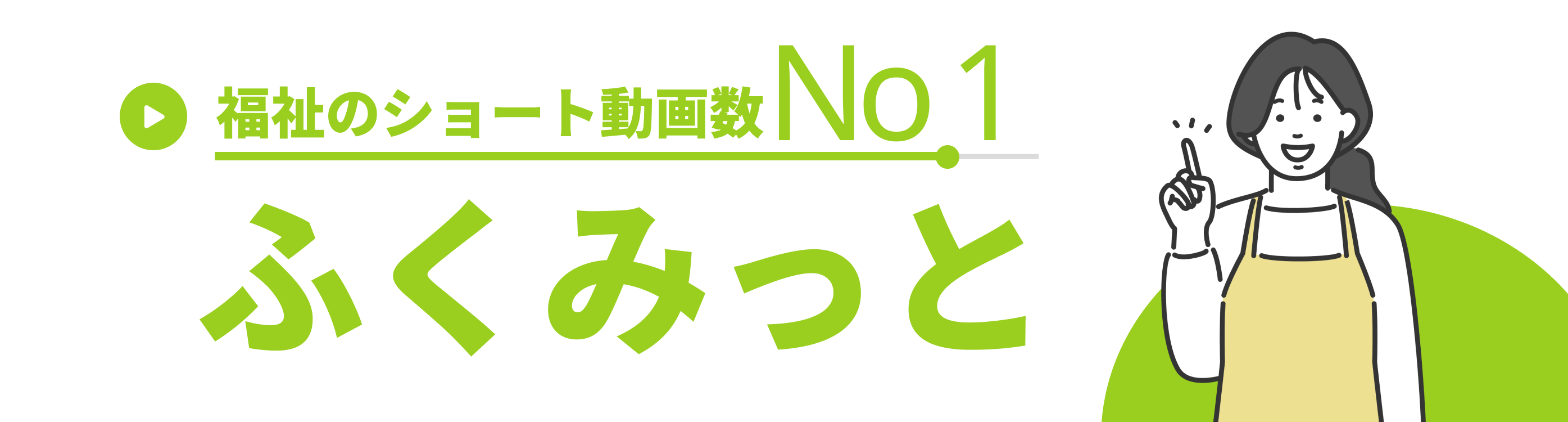
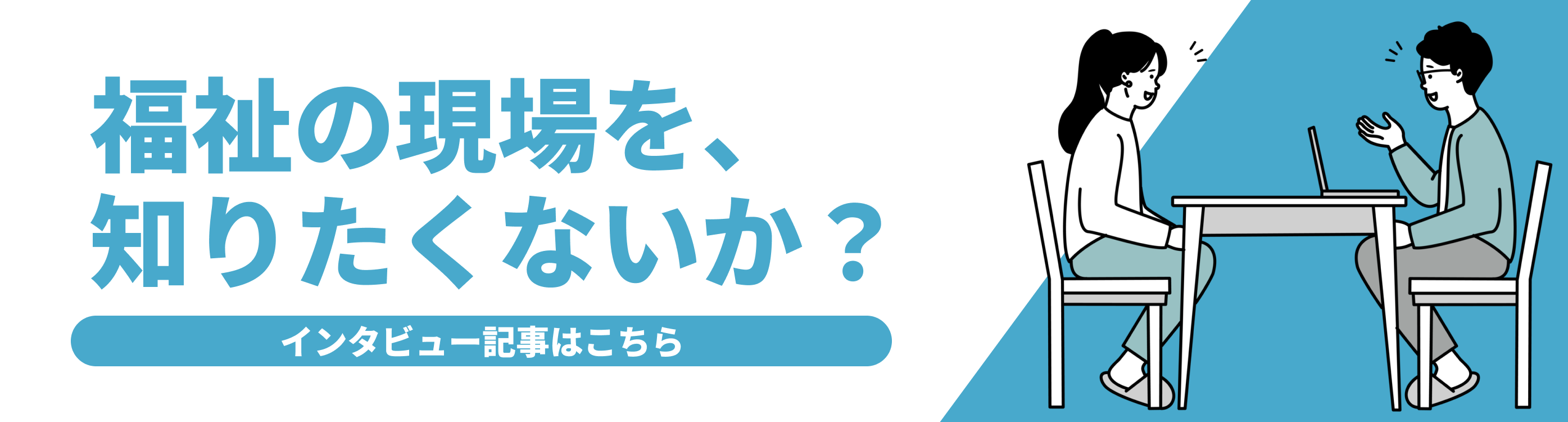

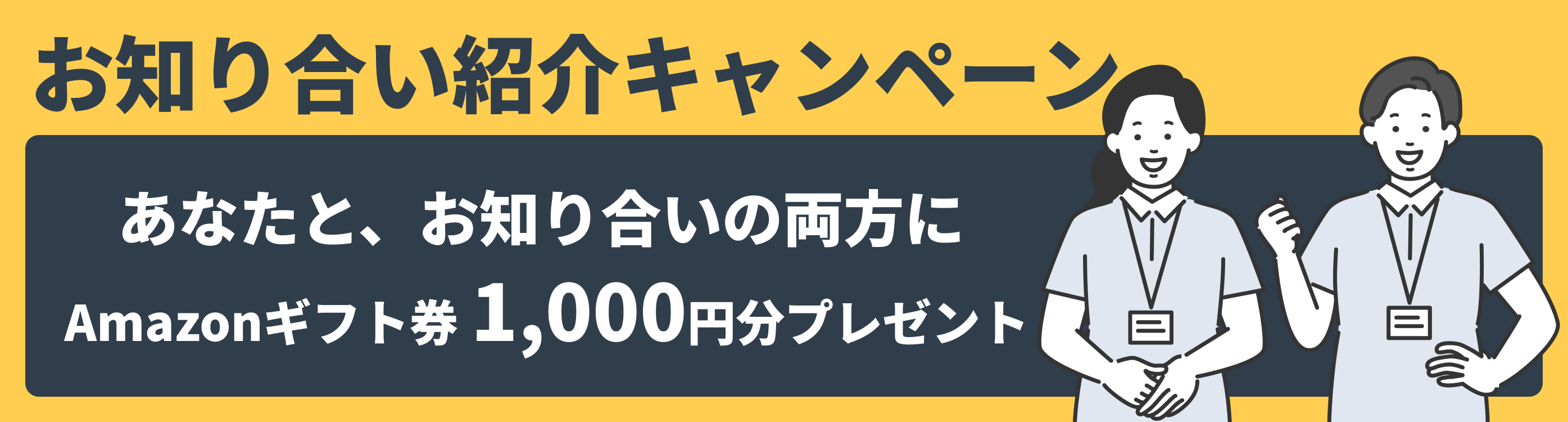

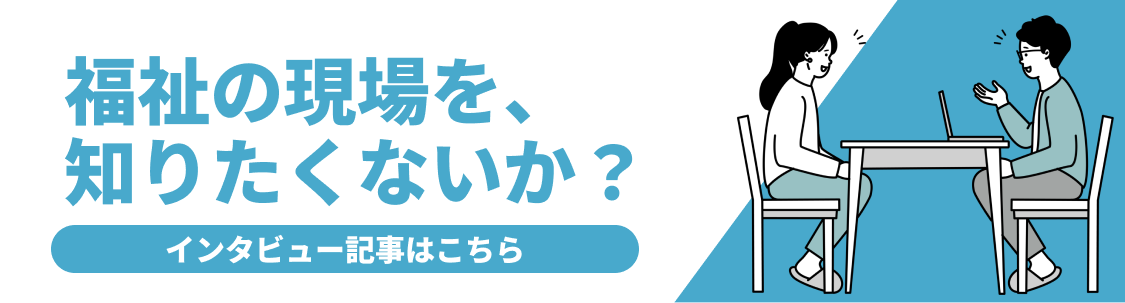

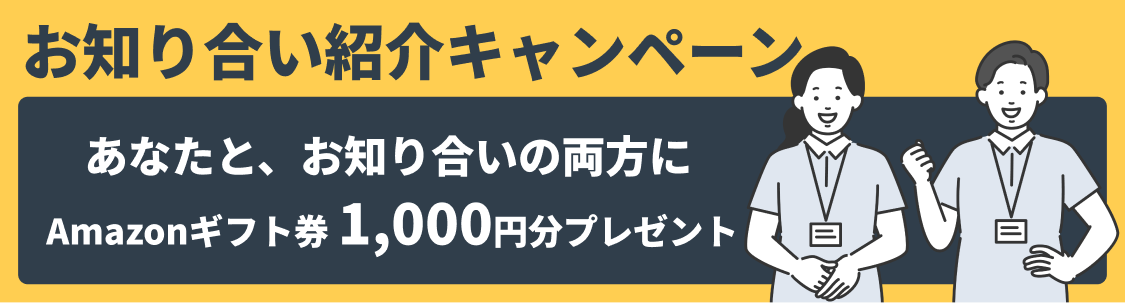







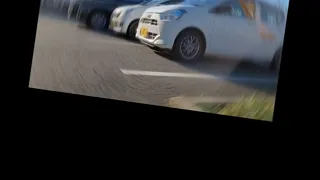


_1661389993371.png)


.png)


























_1686626078023.png)

_1686623665055.png)
_1674618879918.png)